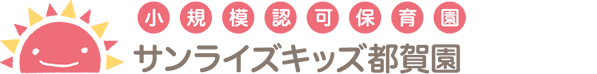2023-02-28ものの見方 0件のいいね!
お子さんと過ごしている中で、どうしても叱ってしまうことや注意してしまうことってありますよね。
どんなにほめるが基本と考えていても難しいものだと思います。
そんな時はお子さんを見る目を変えてみるのも一つのポイントです。
例えば…
「なまけ心」ととるか「なまけ者」ととるか。
「いばり虫」ととるか「いばりん坊」ととるか。
これは単なる言い方の差ではありません。いずれの場合も後者には人格批判的なニュアンスが紛れ込みがちです。
一方前者には「なまけ心」「いばりん虫」が子どもの人格と独立しています。
前者の考え方をすることで、また違った視点でお子さんを見ることができるかもしれないですね。