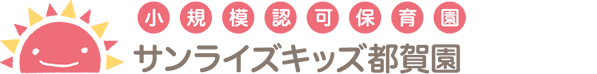2022-07-05脳を育てる順序 0件のいいね!
脳を育てるには順序が大切です。
土台となる体ができていないのに勉強やスポーツを詰め込むとバランスを崩してしまうように、育てる順番は、必ず『からだ脳』からになります。
ある程度体の基礎ができてくると、運動機能を調整する『おりこうさん脳』がつくられ始めます。
そして10歳頃になると、『からだ脳』と『おりこうさん脳』をつなぐ『こころ脳』がつくられ始めます。
3〜9歳頃に手を動かしてのびのび遊び、自分なりに考えた経験や知識を積み重ねることで、『こころ脳』がしっかりと育ちます。