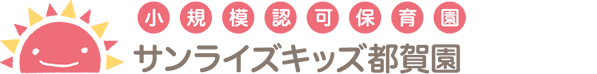2022-04-28汎化(はんか) 0件のいいね!
脳が持つ特徴の1つに『汎化(はんか)』があります。
汎化とは、ある能力が伸びると、別の能力もつられて伸びることです。
鉄道にハマった子が駅名や地名を覚えたり、地理や機械、数字に強くなったりするように、興味を持ったことからそのことに関連する別のことにまで興味が広がり、知識が増えていくのです。
知識が広がる手順や想いが記憶に刻まれ、次に生かされていきます。
トライ&エラーを重ねるうちに、成功体験を積み重ねて自信をつけ、より高度なことに挑戦することを繰り返します。
子どもが失敗への反省を生かしながら新たな一歩が踏み出せるようにしたいですね。