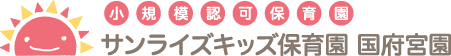2025-11-25脳は3歳までに9割完成ってホント?
55件のいいね!
「子どもの脳は3歳までに9割完成する」って、聞いたことがありますか?
そう聞くと、「何か特別なことをしなきゃ」「もう遅いのかな…」なんて、ちょっと心配になるかもしれませんね。
でも、そんなに難しく考えなくても大丈夫。
脳は3歳をすぎてもどんどん育ちますし、毎日のちょっとした関わりや遊びが、しっかり子どもの力になっています。
この記事では、“3歳までに9割完成”という言葉の本当の意味や、今からできる育脳のヒントを、わかりやすくご紹介します。
「これでいいのかな?」と不安になったときの、ひとつの参考になればうれしいです。
1. 脳の発達はいつ始まるの?
実は、赤ちゃんの脳の発達は、おなかの中にいるときから始まっています。
妊娠中に、細胞がどんどん分かれて、脳や神経のもとになる部分がつくられていくのです。
生まれてからは、まさに“急成長の時期”。
特に生後1年ほどは、まるでスポンジのようにまわりの刺激を吸収して、神経のつながり(=シナプス)がぐんぐん増えていきます。
この時期の脳は、とてもやわらかくて、いろんなことを覚えたり、感じたり、反応したりしながら形づくられていきます。
だからこそ、たくさん話しかけてもらったり、色々なものにふれたりする体験が、とっても大切なのです。
2. 「3歳までに9割完成」の意味とは?
「脳は3歳までに9割完成する」と聞くと、「じゃあ3歳までにすべてが決まってしまうの?」と不安になるかもしれません。
でも、これは“脳の形”や“大まかな構造”ができあがる、という意味であって、すべての能力や性格が固定されるわけではありません。
たとえば、赤ちゃんは生まれたときにすでに、脳の中にたくさんの神経細胞を持っています。
そして、その神経細胞が互いに手をつなぐように「シナプス」というつながりを増やしていくのが、0〜3歳の時期。これは「神経回路の土台作り」ともいえる大切なステップです。
この時期にたくさんの刺激を受けることで、必要な回路が強化され、使わない回路は自然に減っていきます。つまり、3歳までに脳の“ベース”が整い、そのあとに本格的な“育ち”が始まっていくのです。
3. 幼児期に伸ばしたい3つの力
脳がぐんぐん育つ幼児期には、これからの人生の土台となる大切な力が育ちはじめます。ここでは、特に意識して育てたい「3つの力」についてご紹介します。
(1)感情をコントロールする力(前頭前野の働き)
「泣き止まない」「かんしゃくを起こす」など、小さな子にはよくあること。
でも実は、それは脳の“前頭前野”という部分がまだ発達途中だからです。
この部分は、がまんしたり、気持ちを切りかえたりする働きをしています。
親が気持ちに寄り添ってあげることで、「落ち着く方法」や「感情の扱い方」を少しずつ学び、前頭前野が育っていきます。
(2)言葉を理解し、伝える力(言語の発達)
毎日話しかけたり、絵本を読んだりすることで、子どもは「言葉のシャワー」をたくさん浴びます。
これは、言葉を覚えるだけでなく、考える力や人とやりとりする力の土台になります。
たとえまだ話せなくても、声かけはとても大切です。
「あっ、ワンワンいたね!」「おいしいね〜」など、日常の中でどんどん話しかけてあげましょう。
(3)人と関わる力(社会性・共感力)
「お友だちと一緒に遊ぶ」「順番を待つ」「ありがとうを言う」――これらはすべて、社会で生きるために必要な力です。
この力も、家庭の中での関わりや、他の子どもとの遊びの中で自然と育っていきます。
遊びを通して「楽しい」「悲しい」などの気持ちを経験し、人の気持ちを考えられる力が芽生えていきます。
3. 幼児期に伸ばしたい3つの力
3歳ごろまでは、脳の土台がつくられる大切な時期。ここでは、特に育てたい3つの力をご紹介します。
(1)感情のコントロール力
泣いたり怒ったりするのは、気持ちを整える力がまだ育っていないから。安心できる声かけやスキンシップで、少しずつ「落ち着く力」が育っていきます。
(2)言葉を理解して伝える力
たくさん話しかけたり、絵本を読んだりすることで、言葉の力が伸びていきます。まだ話せない時期も、耳からしっかり吸収しています。
(3)人と関わる力
「ありがとう」や「順番を待つ」といった社会性も、遊びや関わりの中で育ちます。気持ちを共有する体験が、思いやりの芽を育てます。
- - - - - - -
まとめ:焦らなくても大丈夫。今できることが脳を育てる力に
子どもの脳は、生まれてすぐからぐんぐん育ち、3歳ごろには土台がしっかり整っていきます。でも、決して「3歳で終わり」ではありません。その後も、経験や関わりを通して、心も頭もゆっくりと育っていきます。
大切なのは、「特別なことをする」よりも、「日々の関わり」を大事にすること。話しかけたり、一緒に笑ったり、絵本を読んだり――そんな何気ない時間が、子どもの脳を育てる一番の栄養になります。
焦らず、比べず、その子らしい育ちを見守っていきましょう。あなたのそばにいる安心感こそ、何よりの育脳です。